一般社団法人デジタル認証サービス機構(Digital Certificate Service Platform 以下、DCSP)は2024年、個人のスキルや知識、コンピテンシー、資格等をデジタル証明するオープンバッジの発行基盤として「オープンバッジファクトリー」を導入しました。
教員免許状のデジタル化をはじめ、多岐にわたる分野でのオープンバッジ普及に取り組んでいます。この取り組みは「すべての人の努力が報われる社会」というビジョンを掲げた社会変革プロジェクトとしての側面を持っています。
この構想の中心人物の一人であり、アドバイザーを務める日本経済大学教授、社会構想大学院大学教授の荒木貴之氏に、DCSPの設立目的、オープンバッジファクトリー導入の背景、そしてその先の展望について伺いました。

デジタル認証サービス機構(DCSP)とは
―― 一般社団法人デジタル認証サービス機構(DCSP)の設立の経緯と目的について教えてください。
荒木氏:DCSPは、日本国内および国際社会における生涯学習の個別最適化を推進し、グローバルな人材流動性を促進することを主たる目的として、2024年7月に設立されました。特に、個人が保有する多様なスキル、知識、コンピテンシー、そして各種資格をデジタル化することを通じて、学習者一人ひとりが自らの学びの成果に誇りを持ち、その努力が正当に評価される「すべての人の努力が報われる社会」の構築を目指しています。私は、この機構にアドバイザーという立場で参画しています。
DCSPの活動は、主に次の3つの柱で構成されています。第一に、生涯学習に関連する講演会や研修会を企画・開催する教育・啓発事業。第二に、生涯学習の個別最適化を具現化するためのスクール経営などの育成事業。そして第三に、国際的な人材流動性を円滑化するための資格認定事業です。
オープンバッジ導入の背景:潜在的人材の発掘へ
―― DCSPがオープンバッジを導入された背景には、どのような課題意識があったのでしょうか。
荒木氏:オープンバッジ導入の直接的なきっかけは、教員免許状のデジタル化という課題への意識でした。昨年、高知県の教員採用試験で多数の辞退者が出たことが報道され、教育現場における教員不足の深刻さを改めて認識しました 。一方で、日本には教員免許を保有しながらも実際に教職に就いていない、いわゆる「ペーパーティーチャー」が非常に多いという現状があります。教員免許の発行数は約570万人であるのに対し、現職の教員は約100万人に過ぎず、約470万人もの方々が免許を活かせていない状況です。これらの潜在的な人材に、何らかの形で学校教育に関与していただく道はないかと考えたのです。
―― 潜在的人材を発掘するという視点ですね。
荒木氏:その通りです。ペーパーティーチャーの方々が持つ隠れたスキルや経験を可視化する手段として、オープンバッジが有効なのではないかと考えました。そして、それが教員不足という課題解決の一助となるのではないかという期待を込めて、この取り組みを開始しました。
この「ペーパーティーチャー」問題は、単なる教員数の不足というだけでなく、社会全体として貴重な専門知識や能力が活用されていないという、機会損失を意味します。オープンバッジは、これらの潜在的な人的資本を「再発見」し、教育現場や関連分野へ「再統合」するための触媒となり得ます。これは、学校での正規教員としての復帰だけでなく、学習支援や地域社会における教育活動など、多様な形での貢献を促す可能性を秘めており、教育リソースの多角的な活用につながるでしょう。
また、この取り組みは現職の教職員にとっても大きな意味を持ちます。自らのスキルや知識、研修歴などをオープンバッジとして可視化することで、自己肯定感を高め、主体的な学びへの意欲を喚起することが期待されます。教職員の資質・能力や学びの軌跡が明確になれば、管理職による適切な指導助言や、組織的な資質向上プログラムの策定も容易になります。さらに、免許保有者が自身の学びを継続的にアップデートし、それをオープンバッジで示すことで、学校現場に留まらず、「社会全体の学びのコーディネーターやファシリテーター」として活躍する道も開かれると考えています。
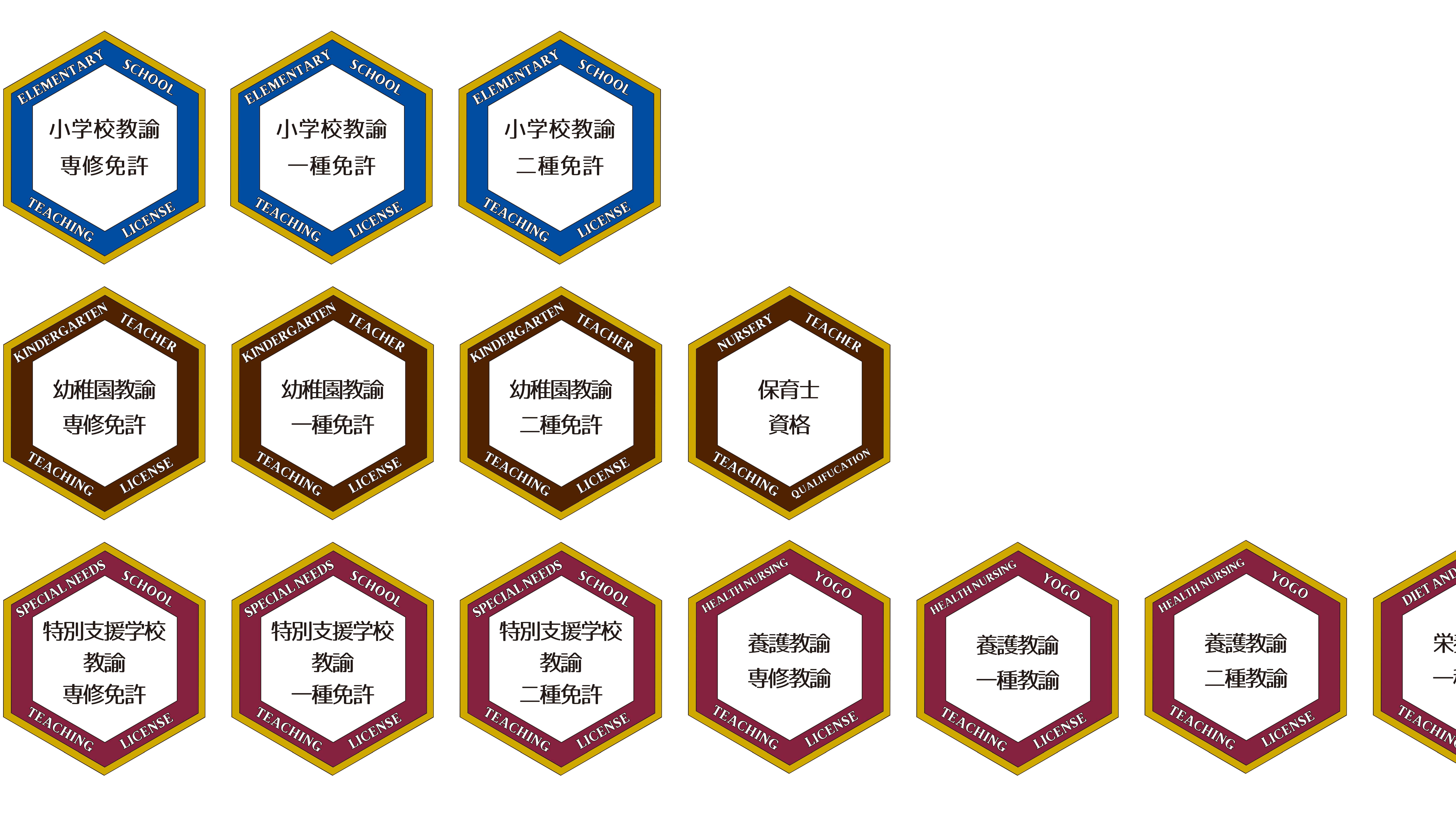
発行済みバッジの種類数は260種類、バッジ発行総数は1786個、バッジ取得者の数は延べ1435名となっています(2025年5月時点)
オープンバッジファクトリーを採用した理由:エンドースメント機能と「人の繋がり」
―― 数あるオープンバッジ発行システムの中で、オープンバッジファクトリーを選ばれた理由は何だったのでしょうか。
荒木氏: 昨年開催された教育業界の展示会「New Education Expo」で、インフォザイン社のブースに立ち寄ったのが最初の出会いです。そこでオープンバッジファクトリーのデモンストレーションを見て、「これは素晴らしい」と直感的に感じました。
―― 具体的に、どの点が特に魅力的だったのでしょうか。
荒木氏: 最も魅力を感じたのは、第三者による「エンドースメント(推薦・承認)」が容易に行えるという点です。発行されるオープンバッジの質と信頼性を担保するためには、他者からの推薦機能が非常に有効です。オープンバッジの国際技術標準であるIMS Open Badges規格の最新バージョン3.0では、このエンドースメント機能が標準でサポートされていますが、オープンバッジファクトリーはすでにこの機能が装備されていました。
また、私自身、以前にB2B(企業向け)のオープンバッジ事業に携わった経験があるのですが、DCSPではB2C(個人向け)のサービス展開をしたいと考えていました。オープンバッジファクトリーは、個人ユーザーが直感的に利用しやすく、その点で非常に優れていると感じました。
バッジ発行の基本的な仕組み自体は、他のプラットフォームと比較して大きな差はないかもしれません。New Education Expoの会場で、インフォザイン社の担当者の方が、私たちの構想や課題に対して親身に耳を傾け、具体的なアドバイスをくださったことも、非常に良い印象として残っています。
―― 担当者の対応の良さも、選択の決め手になったということですね。
荒木氏: はい。その後も担当の方とは頻繁にコミュニケーションを取らせていただきましたし、お話をする中で、予期せぬご縁やつながりがあることも分かりました。複数の選択肢が同等である場合、私は最終的に「人と人との繋がり」や「縁」を重視して決定することも少なくありません。オープンバッジファクトリーの導入決定には、そういった部分での共感や信頼感が大きく影響しました。
導入効果と利用者の声:人生の歩みが可視化される喜び
―― オープンバッジファクトリーを実際に導入されてみて、どのような効果がありましたか。発行状況やバッジ受領者の反応などについてお聞かせください。
荒木氏: これまでに3回の無償発行キャンペーンを実施し、一部バッジの有償提供も開始しています。発行済みバッジの種類数は260種類、バッジ発行総数は1786個、バッジ取得者の数は延べ1435名となっています(2025年5月時点)。バッジの受領率は約80%で、申し込んだ方の多くがきちんと受け取ってくださっています。
―― 受領者の方々からは、どのような声が寄せられていますか。
荒木氏:多くの方から喜びの声をいただいています。直接メールで感謝のメッセージをくださる方もいらっしゃいますし、X(旧Twitter)などのSNSで喜びを表現されている方も見受けられます 。特に印象深いのは、教員免許状のデジタル化のためにエビデンス(免許状の写真など)を送っていただく際、まるで歴史的な資料のような、非常に古い時代の立派な免許状が届くことです。現在の画一的なデジタル化された証明書とは異なり、当時は墨で手書きされていたり、自治体によってサイズや様式もまちまちだったりします。それらを一つひとつ拝見するのは、まるで貴重な骨董品を鑑賞しているような、非常に感慨深く、楽しい時間です。
70歳を超えて既に教職を引退された方々も少なくありませんが、ご自身が情熱を注いでこられた現役時代の貴重な思い出や努力の証を、デジタルという新しい形で残したいという強い思いを感じます 。頑張ってきた証がデジタルデータとして永続的に残り、それが様々な形で共有可能になるということは、個人の幸福感や人生の肯定感を高める上で大きな価値があると思います。もしかすると、何十年という時を経てご自身の教員免許状を改めて手に取り、それをオープンバッジにするというプロセス自体に、大きな喜びを感じてくださっているのかもしれません。
.png?width=200&height=233&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-04-07%2016.17.09%20-%20%E8%8D%92%E6%9C%A8%20ARAKI%E8%B2%B4%E4%B9%8B%20Takayuki%20(1).png)
―― 人生の証をデジタル化するお手伝いができるというのは、素晴らしいことですね。SNSでの共有状況はいかがでしょうか。
荒木氏:SNSへの共有率は、全体で見るとやや低い傾向にありますが、最近発行数を伸ばしている「社会教育士」のオープンバッジに関しては、SNSで積極的に共有される割合が高いです。社会教育士の方々は、社会教育や生涯学習を推進する上で、ご自身の資格をアピールし、関係者とのコミュニティを形成することが職務の一環とも言えるため、共有への意識が高いようです。
一方で、小中学校の先生方の場合、職場の規定などでSNSの利用が推奨されていないケースもあり、共有が難しいという事情もあるかもしれません。オープンバッジは、LinkedInやFacebook、X(旧Twitter)といった主要なSNSで簡単に共有できるほか、メールの署名欄に表示したり、名刺にQRコードを印刷して活用したりすることも可能ですので、それぞれの環境に合わせてご活用いただければ嬉しいです。



オープンバッジの多様な展開とコミュニティ形成への期待
―― 教員免許状以外には、どのようなバッジが発行されていますか。
荒木氏:日本語教師の方々から「ぜひ発行してほしい」というご要望があり、新たに対応を開始しました。
また、国際的な事例としては、ウズベキスタンの国立タシケント工科大学で日本語を学ぶ学生さんたちにもオープンバッジを発行しました。これは、彼らが習得した日本語能力を、日本の企業に対して日本語のメタデータを用いて効果的に伝えたいというニーズに応えたものです。
その他にも、社会教育士、ICTサポーター、保育士といった資格のオープンバッジも発行しています。これらの取り組みの根底にあるのは、従来の紙ベースの証明書や、目に見えにくい能力・経験をデジタル化することで、雇用におけるミスマッチを解消し、新たな雇用機会の創出につなげたいという思いです。
さらに、オープンバッジファクトリーには、学習者同士のコミュニティ形成を促進する機能も備わっています。将来的には、同じバッジを持つ人々、あるいは関連するバッジを持つ人々が、プラットフォーム上で新たなコミュニティを形成し、互いに学び合ったり、協働したりすることを期待しています。
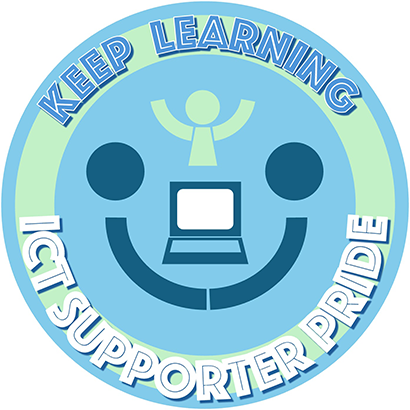
.png?width=200&height=212&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-04-07%2016.19.25%20-%20%E8%8D%92%E6%9C%A8%20ARAKI%E8%B2%B4%E4%B9%8B%20Takayuki%20(1).png)

導入時の様子:関係者の協力により迅速な導入が実現
―― 導入にあたって、ご苦労された点や課題はありましたか。
荒木氏:私個人としては、ユーザーインターフェースの操作性を含め、システム利用面で特に大きな課題を感じることはありませんでした。むしろ、先ほどお話ししたように、発行業務を通じて歴史ある免許状に触れることができるなど、運営する側としての喜びを感じています。
特筆すべきは、最初のキャンペーン開始まで約1ヶ月半という非常に短期間で準備を完了できたことです。これは、多くの方々のご協力とご支援の賜物です 。特に、バッジのデザインに関しては、キャンバサダー(Canva認定教育アンバサダー)であり、Canvaの高度なスキルをお持ちの江藤由布先生に、200種類を超えるバッジデザインの制作をお願いしました。江藤先生はこの取り組みの趣旨に深く賛同くださり、いわば「手弁当」で、ご協力くださいました。
また、教育コンサルタントとしてご活躍の平井聡一郎先生には、最初のオープンバッジ受領者のお一人として、貴重なコメントをお寄せいただきました。平井先生も同様に、この取り組みの意義を理解し、ご協力くださいました。お二方とも、日頃から大変お忙しいにも関わらず、この社会的に意義のある取り組みのために貴重なお時間を割いてくださったことに、心から感謝しています。その熱意が、プロジェクトを力強く推進する原動力となりました。
今後の展開:努力が報われる社会の実現に向けた目標

―― 今後のオープンバッジの展開について、具体的な目標をお聞かせください。
荒木氏:現在の発行総数は約1786個ですが、教員免許保持者が約570万人、現職教職員が約100万人いることを考えると、普及はまだ初期段階です 。当面の目標として、まずは教員免許保持者の3%の方々にオープンバッジを取得していただきたいと考えています。これは、イノベーションの普及理論などでも言われるように、全体の3%が変化を受け入れると、それがトリガーとなってシステム全体に変革が起こる可能性があるという考えに基づいています。例えば、明治維新を推進した活動家も、当時の人口の約3%だったと言われています。
今後も、夏休みや春休みといった長期休暇の時期を捉え、無償発行キャンペーンを継続的に実施していく予定です。普及拡大のためには、SNSを通じた情報発信や口コミによる共有が極めて重要だと認識しています。平井先生のような影響力のある方々に、オープンバッジの価値を認めていただき、その良さを広めていただくことも、大きな力になると期待しています。
―― 対象者を拡大していく計画について、具体的にお聞かせいただけますか。
荒木氏:教員免許保持者に留まらず、様々な資格、個人の頑張りや経験をオープンバッジ化していくことを目指しています。既に、日本語教師、社会教育士、保育士など、教員免許以外の資格についても取り扱いを開始しています。
さらに、小中学校教育におけるオープンバッジの発行も計画しています。総務省の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の一環として、東北学院大学の稲垣忠先生が率いるチームに参画し、初等中等教育や社会教育・生涯学習分野でのオープンバッジ発行に取り組む予定です 。子どもたちや社会人にも、自らの努力や学びの成果が可視化される喜びを体験してほしいと願っています。高校生に関しては、昨年、探究学習の発表会でオープンバッジを発行した実績があり、総合型選抜など大学入試での活用にも繋がる可能性を感じています。
―― 初等中等教育や生涯学習にも対象が広がっていくのですね。それ以外にも構想されていることはありますか。
荒木氏:私自身が今年度、日本経済大学経営学部で人的資源管理論の講義を担当することになったため、大学生たちとも一緒にオープンバッジの活用可能性を探求していきたいと考えています。これからの時代は、人材を単なる資源(リソース)として捉えるのではなく、育成し価値を高める資本(キャピタル)として捉える「人的資本経営」の考え方がますます重要になります。オープンバッジを通じて個人のスキルや経験を可視化し、それを社会全体で育成・活用していく方法を模索していきたいです。
目指す社会像:すべての努力が価値づけられ、キャリアが自己主導でデザインされる未来
―― DCSPの活動を通じて、どのような社会の実現を目指されているのでしょうか。
荒木氏:将来的な目標として私たちが描いているのは、個人の努力の証が社会の隅々まできちんと評価され、例えば入学試験や就職・転職といった人生の重要な局面が、ペーパーテストや面接といった一度きりの選考だけでなく、オープンバッジによって可視化された日々の地道な努力や多様な経験も評価される社会です 。具体的には、図書館で多くの本を読破した経験、海外でのボランティア活動に従事した経験など、これまで評価の対象となりにくかった活動もオープンバッジで表現され、その価値が認められる社会を目指しています。
―― 個人が自らのキャリアを主体的にデザインしていく上で、オープンバッジは有効なツールとなりそうですね。
荒木氏:まさにその通りです。これからの社会では、働き方の多様化が一層進み、ジョブ型雇用も拡大していくでしょう。そのような変化の中で、個人が自身のキャリアについて深く考察し、必要な学びやスキルを主体的に獲得し、それらを効果的に自己管理・ブランディングしていくことが重要になります。この考え方は、個人が自身のデジタルアイデンティティを自律的に管理・運用する「自己主権型アイデンティティ(SSI:Self-Sovereign Identity)」の概念にも通じます。オープンバッジは、このSSIを実現するための有力なツールの一つであると確信しています。
個人が必要なスキルを自ら見極めて習得し、それをオープンバッジという形で明確に社会に示す。その結果、企業の採用担当者や教育機関関係者の目に留まり、個人が学校や企業と直接的かつ円滑に繋がれるようになる。オープンバッジは、そのような新たな可能性を切り拓く力を持っていると考えています。
―― 荒木先生のご研究範囲の広さと、常に「人の繋がり」を大切にされている姿勢が、本日のお話から深く伝わってきました。今後の取り組みも非常に楽しみです。本日は貴重なお話をありがとうございました。
荒木氏:こちらこそ、ありがとうございました。ぜひ今後もDCSPの様々な取り組みにご関心をお寄せいただき、ご協力いただければ幸いです。まずは目標である教員免許保持者の3%への普及を目指し、オープンバッジファクトリーの有用性も積極的にアピールしていきたいと考えています。
【オープンバッジファクトリーとは】

オープンバッジファクトリーは、デジタル証明としての国際的な技術標準規格であるオープンバッジ 2.0に準拠した「オープンバッジ」を作成・発行・管理するためのプラットフォームです。
公的な資格試験の合格証から、講座の修了証、イベント参加証、スキル証明や、ゲーム感覚の楽しいバッジ集めまで、教育機関だけでなく、NGOや企業内での人材育成など、子どもから学生・社会人まで、さまざまな用途に対応します。
修了証の発行をデジタルバッジで行うだけでなく、既存の学習活動にオープンバッジを適用することで、マイクロクレデンシャルの導入やゲーミフィケーション化が可能になり、学習成果をより明確かつ魅力的に示すことができます。
オープンバッジファクトリーの概要やサービス内容・プランの詳細など詳しくは下記リンクをご覧ください。
オープンバッジファクトリーの詳細はこちら

ITと教育の分野でのイノベーターとしてのインフォザイン

「株式会社インフォザイン」は、東京 上野にオフィスを構え、教育とテクノロジーを融合させたEdTech分野でビジネスを展開しています。
「オープンソースとオープンスタンダードを活用し、教育の未来を創る」ことを目指し、特に力を入れているのは、ルクセンブルクのOAT社が開発したWebベースでアセスメント・テストを実施するためのCBT(Computer Based Testing)プラットフォーム「TAO」をベースとした新サービスの開発と提供です。
オンラインアセスメントのためのSaaS版CBTプラットフォーム「TAOクラウドJP」をはじめ、学力調査、大学入試、各種資格・検定試験などのCBT化に実績のあるアセスメントサービスを提供しています。
また、学習歴の可視化の手段として利用が広がっているオープンバッジの発行プラットフォーム「オープンバッジファクトリー」の日本における独占販売契約を締結し、サービスを提供しています。
なお、教育DXを推進するため、教育に興味を持っているITエンジニアはもちろん、教育分野に課題意識を持っている人材も広く募集しています。
サービスや採用情報などへのご質問もお気軽にお問い合わせください。
【お問合せ先】
株式会社インフォザイン
e-mail:obf@infosign.co.jp
公式HP: https://www.infosign.co.jp/
〒110-0008 東京都台東区池之端1丁目2-18 NDK池之端ビル4F